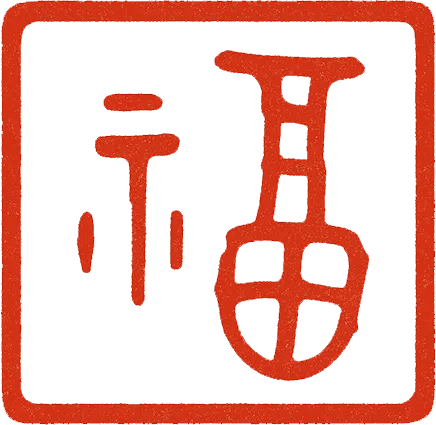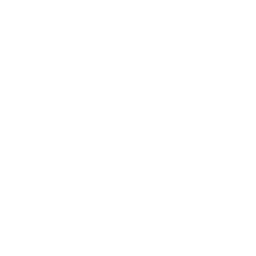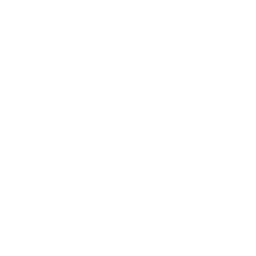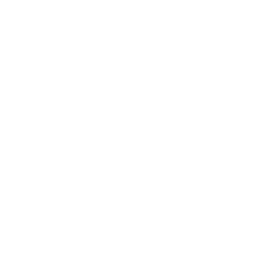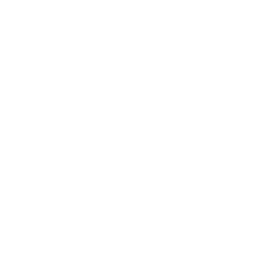青磁「龍泉窯」で日本の徳利
半年かかって、玉壷春の形の徳利とコップセットを完成して、日本市場に提供いたします。
龍泉窯青磁は、中国浙江省龍泉県を中心に発展した青磁(青い釉を施した陶器)の総称です。中国南方青磁系の代表的な窯元として、北宋初期に創始され、南宋中期から後期に全盛期を迎え、明代中期以降は衰退し、清康熙年間まで生産が続きました。約700~800年の長い歴史を持つ世界で最も長く焼造を続けた窯場の一つです。
南宋時代の龍泉青磁は「人造の美玉」と称され、海上シルクロードを通じて日本、朝鮮半島、東南アジア、中東、ヨーロッパに輸出され、世界の陶磁器文化に大きな影響を与えました。特に日本の「砧(きぬた)青磁」や韓国の「高麗青磁」は龍泉青磁の技術と美意識を吸収しました。
2009年、龍泉青磁の伝統焼成技術がユネスコの「無形文化遺産」に登録されました。

各時代の特徴
北宋(10~12世紀)
- 胎土:厚手で淡灰色、底部(露胎部分)に赤褐色の窯焼き色(窯赤)が見られる
- 釉薬:透明感があり、光沢が強く、デコレーションは魚紋、蕉葉紋など簡潔な模様が主流
- 特徴:豪放なデザインが好まれた
南宋(12~13世紀)
- 釉薬の進化:石灰アルカリ釉を多用し、粉青(淡青)、梅子青(緑青色)などの美しい釉色が完成
- 造形:鳳耳瓶、鬲式炉など、重厚で洗練された器形が特徴
- 装飾技法:刻花(彫刻)、堆塑(立体装飾)が発展し、精緻な工芸と文人の好みが反映
元代(13~14世紀)
- 造形・胎土:器形が大型化し、胎土は白中に灰色や淡黄色
- 釉薬:粉青に黄緑の調子、半透明で光沢が強く
- 装飾:雲龍紋、八仙紋など豪快な模様が主流。漢字や八思巴文字の銘文も見られる
明代(14~17世紀)
- 特徴:胎土が厚く、灰色や黄色調、釉色は青灰色、茶色系が増え、工芸は粗雑化
- 装飾:刻花が主流だが、人物故事の模様も見られる
陶磁器の知識を学びながら、商品の美しさをもっと味わいます。